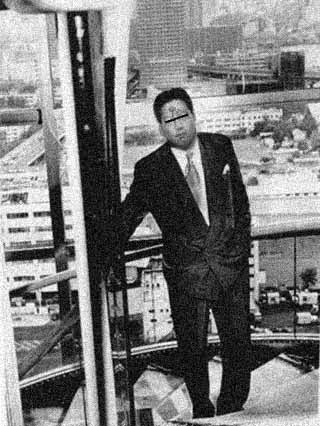|
|
|
マンガが好きで、ある程度以上に読み込んでいると、色々と語りたくなるモノだ。それは全く、あって当然のことだろうし、悪いことではない。しかし、忘れないようすべきなのはその立ち位置だ。自分がどういった立場でそれを述べているのかと言うことだ。好きとか嫌いとか、そういう発言にも意味はある。あるが、それは読者の立ち位置だ。それ以上の何かを語ろうと思ったときには、その時点で立ち位置がただの読者ではなくなっている。その事を、心して語ろう。何かについて語るというのは、そう言うことだ。 |
表紙 最新 Backnumber 01 02 |
ジャンプのワンピースってそんなにおもしろいでしょうか!?最初、友達はみんなおもしろいといってたので、まあ、ヒトの好みはそれぞれだしな、と思ってたんですが、最近大人気みたいでよく巻頭カラーでやってたりします。 僕からみればそんなドキドキワクワクな展開じゃないと思うし…絵は個性はあるけどそんなに魅力ある絵とは思わないし…。 すんごい話もひねってるようには思えないし…感動できないし。 こんなに人気があるのがわかんないです。 今のはかなり個人的な意見ですが、かなりマンガマニアなヒトが見てると 思われるコミック・ゴン!のオキニレーティング(笑)でも尾田栄一郎さんの名前は一回ものったことないです。(Dランクにさえ…) これってほんとにおもしろいんでしょうか? もちろんマンガの水準ぐらいはあるとおもうんですが… こんなに他のヒトと意見が合わなかったマンガってはじめてです。
|
・俺は好きだよ。ただ、それは俺が長いことジャンプを見てきていたからと言うことも原因としてあるかもしれない。 あの作者は、確かに巧い。 その“巧さ”は、いわゆる“ズラし”にあると思う。 つまり。 ジャンプマンガらしくない、という事だ。 ジャンプマンガの手法、というものがコチコチに固定化して出来上がっているという流れがあり、その流れに閉塞感を感じていた古い読者が居る。 その古い読者にとって、『ONE−PEACE』の展開は、かなり爽快感のあるものだ。 例えば、今の“ナミ”の話もそうだ。 ナミというキャラが登場したのはコミックスにしてもかなり前だ。 その“古い”キャラクターの根幹のストーリーが今になって描かれている。 行き当たりばったりで“その週の評価のみ”に重きを置いていた数年前のジャンプの手法では、こんな長い伏線は許されていなかった。 しかも、その出し方が心憎い。 水上レストランからの流れの中で、決して大上段に構えずに読者の興味を擽る。 彼は、その辺の流れを非常に良く心得ていると思う。ストーリーラインの流し方が、ジャンプであるという事を踏まえた上で、さらに巧みに組み立てている。 巧さを全面に出さない巧さ。 それまでも持っている。 おそらく、“古くからのジャンプ読者”のココロを擽っているのはそういったあたりでは無いだろうかと思う。 勿論、新しい、年若い読者にとっても十分な魅力は持っていると思うが、俺があの作品を読んでいるのはそういった理由だ。
蛇足ながら。 『コミックGON』は俺も読んではいるが、あそこの評価は信用していない。 ハッキリ言って、サブカル根性丸出しで『穿った見方』をすれば『格好良い』と思っている様な連中が、『一般のマンガ読者をバカにする』ことで『マニアを自称する人間に媚びている』としか、俺には思えないからだ。 データベースとしては価値があるが、書評には殆ど中身が無いと言っても過言ではないだろう。 (何せ、『ベルセルク』の事を『エヴァンゲリオン』や『北斗の拳』のパクリだ、等と言うほどの連中が作っているのだからな) |
同人誌。これについては意見が分かれるところだと思うけど。ある人は感情移入したキャラクターを他の人が書いてるだけで嫌がる。だけどある人は漫画の世界が広がるといって好意的な意見。 私は後者ですね。 でもある時、友人がらんまのファンで単行本とか集めてたのを知っていたので、[こんな同人誌でてるぜ]とそれを見せたら[何だよこれ!]とショックをうけてました。なぜならそれはエロ同人誌だったから…。 同人誌があるってことはもちろん書いてる人がいるし、それを望む声があるって事。その漫画の原作者の著作権とかは解らないけど、本人にしたらあまりいい気はしないと思う。まして出版者には百害あって一利無しって訳で…。とくにエロ同人誌は。 なんか捕まったって話もきいた。[ピカチュウ×サトシ]ってエロ同人誌を販売してた人が任天堂に訴えられたとか。 メーカーとしてはある意味人気のバロメータでもあるから、黙認してた部分もあると思うけど。これの場合は年齢層が低い漫画をエロくしたから黙ってなかったらしい。 同人誌を書いてる人ってみんながみんな金の為にやってるとは思ってないよ。なかには同人誌をかいて同じ作品に興味をもった人に出会いたいとか、多くの人に見てもらいたいとか。そういう人も多いと思う。その漫画が好きだからこそ、それ故同人誌を書いてるんだと思うし。 エロ同人誌については、、、う〜んどうかな〜、と思うところもあるけどね。でも、なくらないよねこれは。どんなに規制しても無駄だと思う。それを書く人と買う人が耐えないから。 私は同人誌が好きですね。別にエロくなくてもいいけど。なんかどの作品も原作に対する、なんつーか愛情? みたいなものであふれてるから。方向性は間違っていてもそれはそれでいいんじゃないでしょうか……。 このことについて、どう思いますか?
|
・基本的には、否定も是正もせず、だな。いわゆる、パロディとしての同人活動を指しての話だよな。 俺個人の考えとしては、基本的には反対はしない。活動そのものには、な。 表現活動、という意味でなら、パロディも一つの手段だ。それを否定すること自体は、創作という観点で見た場合は不可能ではある。 ただ、どんなモノでもそうだが、パロディにも出来不出来はある。そして、パクリとパロディは全く別のモノだ。 いわゆる、ポルノグラフィとしてのパロディに関しても、基本的には変わらない。 問題は、パロディという表現手段、であって、ポルノグラフィとしてのパロディというのは、アダルトコミック(小説なども含む)に関する問題として考えるべきモノで、パロディである、という視点と、ポルノである、という視点はそれぞれ別の問題としてとらえる必要はあるだろう。 パロディという表現手法で作られた作品にも、優劣がある。 俺は、優れた作品として成立していれば、賞賛するし、愚劣な出来のモノであれば歯牙にもかけない。 著作権、という問題がある。 著作権というのは基本的に民法に属する法律だ。 つまり、著作権を所有しているモノが「侵害である」旨訴えて、初めて罪であるかが問われる。 著作権は、当然守られるべき権利だ。 しかし、その基準が実に微妙なものであるという現実がある。 俺は、意図的に他者の創作物の権利を侵し、利を得ようとする行為を是正するものではない。 ただ、何を持ってして侵害とするかの基準は、非情に曖昧であると思う。 いわゆるパロディとしての同人活動をしている人間のウチの幾人かが、これらの権利に関して無自覚である現実は、問題だろう。 パロディ同人を描く者は常に、自分がやもすれば他者の権利を侵害してしまう可能性のある行為をしている自覚がなければならないだろう。 商業的側面に関しては、さらに微妙な問題だろう。 聞いた話だが、ある同人作家が印刷所のミスを責めるときに、「こちとらこれでメシ喰ってンだ!!」 と言ったという話もある。 それぐらい、確信犯的にパロディ同人誌を商業活動としてとらえている人間もいるようだ。 こうなってくると、同人誌ではないだろう。 自費出版、という方が呼称としては正しい。 この場合は、著作権使用を申請するなどの手続きをするのが本来正しいのだろうと思うが、音楽業界などと違ってシステムが出来ていないので、どうとも出来ないと言う面もある。 マンガ業界そのものが、或る意味でパロディ、模倣、そしてパクリといった行為を一括りにして消極的に是正してきていたという背景がある。その流れで、なし崩し的に現状の様な著作権軽視的な体制が出来ているというのもあるだろう。 何せ、企業としての出版社が、堂々と許可も取らずにパロディアンソロジーを出版してしまうぐらいなのだから始末が悪い。 (実際にあった事例は、『トライガン』の作者のホームページに書かれている) これは、システムの問題でもある。 しかし反面、システム化してしまうとその時点で、あらゆるパロディ同人の存在を認めたという事になってしまうという側面もある。 何れにせよ、同人誌という枠では括れない問題だろうと思う。
単純なパロディ同人誌の事に話題を戻そう。
俺がいやなのは、そういったパロディ同人誌を作っている人間のウチ何人かの者たちが、やたらと自分達の権利と正当性を主張したがる事だ。 自らの活動を誇りに思うことは構わない。 創作する立場であれば、それはある意味で重要なことだろう。 だが、他を引きずり落とすことでアイデンティティを確立しようとする様なやり方でそれを誇示しようと言う輩がいるのが気に入らない。 どこにでも、志が低く品性の劣る人間は居るものだが、こういう立場の人間がそれをやったらお終いだろうと、俺は思うよ。
最後に蛇足ながら、知っている範囲で『ピカチュウ同人誌』についての話を書き加えさせて貰う。 あの事件の最大の特徴は、『ピカチュウ同人誌』の作者が『複製権の侵害』で、『刑事事件』として起訴されたことにある。 前述の通り、『著作権』は民法だ。そして、『複製権の侵害』というのは、いわゆる『バッタもののブランド製品』を制作、販売した場合などに適応されるのが一般的な刑法だという。 総じて、この『ピカチュウ同人誌事件』というのは、同人誌、という枠のみならず、非常にに大きな問題をもつ事件だったようだ。
まとめると、『パロディ同人』というカタチでの活動そのものを否定はしない、という点と、それを行う者は常に権利侵害の可能性を考慮して行うべきだろう、という事が主な俺の考えだ。
|
・同人誌禁止派同人誌は漫画家の卵にとっては実習にもなり、まんがに興味を持つ人も増えるなどという理由などもあり、ある程度作家や出版社に黙認されているところがあります。しかし同人誌は存在してはいけないと思います。理由はいくつかあります。 まず、作家(オリジナル)への配慮という点です。 作家はおそらく何日も何ヶ月も悩んでキャラクターを考えるでしょう。いわゆる「産みの苦しみ」というやつです。それを同人誌作家はささっと真似してアダルトなり、パロディーなり、作家のイメージしていたキャラクターへの考え方、作品のイメージなどを壊してしまいます。 同人誌作家も全くオリジナルのキャラで漫画を書けば良いのですが、残念ながらほとんどが既存の漫画を真似たものです。 さらに悪質な同人誌はオリジナル作品を見ている読者にも迷惑がかかります。以前新聞にも掲載されていたポケモンの同人誌などが良い例です。任天堂は会社のイメージを汚すことにもなるという考えがあって訴えたわけですが、実際問題としてその同人誌を読んでしまった、ある意は存在を知ってしまった人にとっても、作品に対するイメージを壊してしまったことになります。 昔、手塚治虫の画風を踏まえ、それをもとにオリジナルキャラの同人誌を発行し、一流の漫画家を目指したような良い意味での同人誌作家活動はとっくに終わりました。作家や企業、読者に害を与えるような同人誌は厳しく取り締まるべきです。 |
・パロディ同人に関しての基本的な考えは前の質問で書いた。だからすこし、論点をずらそう。 パロディ同人の存在は、マンガ、アニメ、ゲームの各業界において或る意味重要な要素となっているという事実はある。 ぶちまけて言えば、そういった活動をしている人も“読者”であり、“消費者”であるという事だ。 そして、私見であるが特にアニメなどは、そういった“パロディ同人”を行っている人間をあからさまにターゲットとして企画、制作されているモノが多いように感じられる。 悪い言い方になるが、持ちつ持たれつの関係が、現実として其処には存在している。 何らかのガイドラインが必要だという意見には、一理ある。あるが、おそらくは現状では難しいだろう。 例えば、パロディ同人誌を許可制にしたとしよう。 音楽などの使用と違って、そのものを使うワケでは無い。 別の創作物として作られる以上、内容を見て、判断する必要が出てくる。 それにはおそらく膨大な労力がいることだろう。 そして、もう一つ。 上記の“明らかにパロディ、エロパロにされることを前提として企画、制作されているモノ”というのは、より深くそれに接している人間にしか分からないカタチで世に流れている。 ガイドラインとして基準を作ると言うことは、世間に対して“この作品は子供向けアニメの体裁を取っていますが、実はポルノグラフィとしての二次使用を前提とした作品なのです”と公表するようなものだ。 それは、当事者としては避けたい事態だろう。 日本人の国民性というモノもある。 有り体に言って、欧米人などに比べると日本人は観客に徹するのが苦手であると言える。 日本に“評論”という文化が根付きにくいのもそこいら辺が原因らしい。 つまり、“踊るアホウに見るアホウ…”といった感覚だろう。 何れにせよ、制作者側は必ずしもパロディ同人誌という存在を害のあるモノとは考えていない部分がある。利害のバランスを、制作者サイドがどのようにとらえているかによって対応は全く変わった物にならざるを得ない。そして、その基準を明確化することを望んでいる制作者は、恐らくあまり多くはないだろう。 |
漫画家の同人活動って…?プロで同人誌かいてる人がいると聞いたんですが、それって同時進行でですか? プロでやってるほうで全力注げと思うのは私だけ? プロになったら、趣味でマンガ描くのはもう卒業でしょう。趣味で描いたヤツを読みたい人って多いんですかねぇ、理解できないですね。 |
・趣味で描くということは、別に仕事でやるという事の下にあるものじゃない。だから、仕事で漫画を描きつつ、趣味でも漫画を描くと言うことは決しておかしな事ではないよ。 例えば、F1ドライバーが、休暇に一人で峠を飛ばす事があってもいい。 シェフが休日に仲間とバーベキューパーティーをやったっていい。 歌手がカラオケで歌うことだってある。 マンガを描くという行為そのものを言えば、ある意味特別な事だろう。 だが、それを仕事としてとらえた場合は、何等特殊な事柄ではないよ。生きていくための手段だ。 考えようによっては、むしろ仕事と趣味でキッチリやる事を分けているというのは、プロとしてのしっかりした意識の現れだとも言える。 |
パロディーは良くないと思う。私はパロディーに関しては、あまり良いとは思っていません。正確に言えば使い過ぎは良くないと思います。 ある作家が別の作家のキャラクターなどを用い、自分の漫画に登場さた場合、その時点でパロディーです。 昔の作家は一話にたいして数コマ程度扱う程度でした。この数コマが私は良いと思います。別にパロディーでもほんのすこしなら私は良いと思います。 ただ問題なのはその量です。 はっきり言ってしまえばパロディーという技術は「イマジネーションを用いない技術」に他なりません。 とりあえず他作家のキャラを登場させた場合、そのキャラを知っている読者は当然「ニヤリ」とするなりして、とりあえず読者の笑い、受けを取れるのです。 この受けと笑いはその作家の技術ではなく、別の作家のおかげで成り立つわけで、全く省エネでずるい技術だと思います。これを少々するのであれば演出として通りますが、それが多すぎたり、あるいは全部などの漫画はどうかと思います。 ですから商業誌作家がパロディ同人誌を作ること、などはもってのほかです。 |
・パロディという表現手法確かに、「そこそこウケの取れるもの」を作るのは簡単だろう。 俺も経験があるから、それは分かる。 いわゆる、「パロディ4コマ」とか、それに類するものである程度のモノを仕上げるのにかける労力は、全くのサラで考え始めるのとではまるで違う。 だが、あえて言おう。 パロディをするのにもセンスはいる。 鋭い着眼点を持ち、それを巧みに並べ替え、他の人間が意外に思えるような発想の転換をし、再構成するという行為は、氏が思っているほど『誰にでも出来る安易な行為』では無い。 試しに、作ってみると良い。 『面白いパロディ作品』を。 難しいよ。ほんとうに、難しい。 創作手法として、『帰納法』というものがある。 一つのカタチをもとにする。 そこから、「何故?」「どうして?」 等と根幹へと考え方を進めていくやり方だ。 パロディ作品を作るときに必要なのは、その『帰納法』の考え方だ。 これは、例えば『歴史物』を描くときなどにも使われる。 一つの事柄に対して、掘り下げるカタチでアプローチすると言うことだ。 くだらないパロディが無い、等とは俺は言わんよ。 氏の言う、下らなく、やもすれば悪質であるパロディも存在する。 他者の権利を明らかに侵害し、寄生虫のように利潤だけを吸い取ることを生業としている者もいる。 だが、敢えて言わせて貰う。 パロディという表現手法そのものは、「想像力のない人間の使うくだらない手法」等では、決して無い、と。 |
ブラックジャックはヒューマンドラマなの?主人公が時々間違った行動をとるのがあまり好きでないです。 どうも正義の概念がときどき偏ってるような気がします。 公的な職業の医者にしては私情に流されすぎなのかな? いいエピソードも結構あるけれど、(ゲラの話とかは良かった) 最初の話でブラックジャックが出てきた時、暴走族のぼんぼん息子(名前はアクド)を見事に見殺しにします。 医者としてはこんなこと絶対やってはいかんとおもいます。 暴走族って「一人の人間」として見過ごすことのできない死ぬほどの悪人ではないでしょう。 テーマとはそれほど関わり合いのないところで私情に流されがちに感じます。 ドクターキリコとか本間先生とかテーマに沿ったところの問題提起は今でさえ、考えさせるところがあります。
ドクターKは割とどうしようもない悪人でさえ医療の手を差し伸べるところが感動ものです!(力説) 僕は「医療の手は万人に平等に与えられるべき」というドクターKの信念が好きなんです。 これはブラックジャックにはなかった考え方だと思うしね。(ドクターK宣伝)
漫画的な手法により、登場人物を実際より悪人に祭り上げ、それを正義と認識させるようなエピソードがいくつかあるのが人道漫画として完成度を暴落させているように思えます。 要するに正邪の概念が時々漫画的すぎるかと思います。 こういう人道を扱ったヒューマンドラマでは媒体がたとえ漫画でも何が正しいか? という部分に漫画的手法を使いすぎないほうがいいと思います。 ブラックジャックの絶賛されているところもこの部分ですから。 俺としてはここらへん一見荒唐無稽に見えるドクターKの方がよくできてると思います。 |
・ブラックジャックのキャラクター性ブラックジャックのキャラクター性は、決して単純な善性や正義漢ではない。 そこが嫌いだ、というのは構わないだろう。主観的な価値観に基づく判断だ。 しかし、それは意図的に創られたキャラクター性であるということも忘れてはならない部分だと思うよ。 彼の精神の根幹にあるモノは、“正義感”でも、“ヒューマニズム”でもない。 俺が思うに、それは言うなれば“足掻き”だろう。 生への足掻き。死への足掻き。医療技術の限界に対する足掻き。そして、総ての運命への足掻き。 幼い頃に五体をバラバラにされるほどの重傷を負うという運命。そして、そこから生還するという奇跡の運命。
ドクターKは、己の医者としての運命を受け入れることからキャラクターとして成り立てって居る。 医者の一族であるということ。そして、それを受け継ぎ、後世に伝えていくと言うこと。 彼にとって、運命は厳しくはあるが、是正できる信念として内にある。
しかし、ブラックジャックは違う。 彼は、運命を否定している。否定することで、自らを無理矢理支えている。 人は何故死ぬのか? 人は何故運命に苦しめられるのか? その、出るハズのない答えと、彼は必死で戦い、足掻いている。 彼の行動、彼の言動に矛盾があるように感じたとするならば、それが原因だろう。 彼は、高額な金銭を要求する。 それは、例えば無人島を買い取り、失われつつある自然や動物を保つために使われることもある。 しかし、それは果たして人道的な思いからの行動なのだろうか?
足掻きであろうと、俺は思う。 情や、気まぐれも、一つの運命だ。 偶々目の前で死にそうになっている者が居る。そして偶々その者を助ける術を持っている。それは、一つの運命だ。 偶々、本間先生に施術してもらえたかのように。 その運命を、彼はただ素晴らしい奇跡として受け入れられないで居る。 何故なら彼にとって、生きると言うことは過酷な運命そのものだったからだ。 彼にとって、生きると言うことは即ち足掻くことなのだ。 生きると言うことに安寧としている者を彼は憎む。 生きると言うことを当然の権利とむさぼる者を彼は否定する。
足掻くもの。生きると言うことに足掻くもの。
それを計る一つとして、彼は多額の金銭を要求するのだと、俺は思う。 例えば、姉の胎内で生き続けるという運命。 例えば、巨体を支え切れぬ心臓で生きるという運命。 例えば、絶滅の危機に瀕するという運命。
そういった運命との葛藤。その絶えざる闘いこそが、彼が生きると言うことに自らが見いだした糧なのだ。
『ブラックジャック』がヒューマンドラマと言われているのは、決してヒューマニズムに溢れているからでもなければ、物事の正否を正しているからでもない。 そこに、生身の人間の苦悩を描いているからだ。
最後に、順不同ながらも最後に、ブラックジャックは電車の中での夢を見る。 かつての人々と、会うことの叶わぬ人々との邂逅の中、彼は足掻くことの無意味さを知らされる。 それでも、彼は生き方を変えることは出来ない。 虚しいと知りつつも足掻くことでしか、彼は自らの生を認めることが出来ないのだから。 |
絵の変わる漫画家いきなりですけど。 だんだん画質が変わっていく作家さんけっこういますよね。画質ってたとえば最初の方はこんな顔だったのに、みたいな奴。ほらコチカメとか、昔の両さんと今の両さんて顔ぜんぜんちがうじゃないですか。まぁ、作家さんがだんだんうまくなっていくんだからいいじゃないか…。って思いますか? 私は思いませんね。 [帯をギュッとね]とか最初から読んでるんですけど明らかに違う。今とは。 …だれでもそうなのかも知れませんね。おおかれすくなかれ。 でも、それをいいとは思いません。なかには昔の方がよかった、って人もいるでしょうし。やっぱり少し位はショウがないかんじがしますけど、原因はなんでしょうか? 絵が変わっていくのは。それは昔は一人で書いていたのに、大量に書かなければならないためアシスタントを雇ったから。とか、昔の画質ではいまはうけないから。とか色々でしょうね。 ナガイゴウ先生とかは変わりませんよね。でも今でも連載してらっしゃる。それにアメコミとかは大量にかいてる割には作者の画質が保たれてますよね。 [変わらないことは、変えることより難しい]ってことなのかな〜。私はだんだん画質が変わっていく漫画を見ると寂しい気持ちになります。なんか作品が、作者がちがくなっていくようで…。 こんな気分になるのはわたしだけでしょうか? ご意見を。 |
・基本的に、不可能だろう。言い換えればそれは一人の人間に対し『一生成長も変化もしないで欲しい』というようなものだからだ。 意図せず、変わることもある。 意図的に、変える場合もある。 そして、 意図的に変えない場合もあり、 ただ意味もなく変化しないこともある。
新人の作家であれば、変わるな等というのは酷なハナシだ。基本的に、成長期にある。そして、まだ自分のスタイルに満足もしていないだろうし、成長に対する意欲もあるだろう。 例に上がった河合克俊等は、『帯をギュッとね!』が、初連載だろう? そういう状況でなら、変わらない方がどうにかしている。
ヒトは絶対的に変わる。 好悪に関わらず、様々な事情、様々な理由で、変わらざるを得ない事もある。 変わることが人間の基本である以上、それを責めるのは酷だよ。
勿論変わらない、という事が悪いとは言わないよ。 それもそれで理由のある事もある。 例えば、変わる必要がない、その必要を本人が感じていない場合等は、変わらないだろう。 一つのスタイルとして完成している、という事もある。 本人に成長の意欲が無い事もある。 だが、何れにせよ、ただ“下手なまま”でないというのならば、それは本人が意図的に選択したことだろう。善し悪しは別として。
とにかく、“変わる”という事は基本的なことだと認識しておいた方が良いだろう。 それは、アメコミのアーティストであろうと、大作家であろうと同じ事だ。 永井豪だって、デビュー当時と今では絵柄は変わっている。それは、恐らくキミがその変化を目にしていないというだけで、変わってはいるのだ。ただ、キミがそれを知らないと言うだけのことで。
繰り返しになるが、変化することを責めるのは酷だ。 しかし、その結果が受け入れられないと言うのなら、それを否定するのは構わないだろう。 それは、自分の感性の問題だからだ。 かくいう俺も、最近では『GENERATION-X』のアーティストだったクリス・バチャロの絵柄が、ゼロ・トレランスの最中に切なくなるほど変な絵になってしまい、とても嫌な気分になった。 まあ、そういうとこかな。 |
●まだまだ物足りないぜ● |
|
|
|